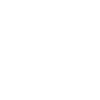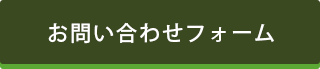使用者からの退職勧奨・解雇についての相談
相談内容
社員10名ほどが働く企業を経営している。先日、A社員を採用した。A社員と以前からいる社員とで仕事の進め方をめぐってもめごとになった。A社員から、「仕事の進め方に従うことはできない。私の仕事のやり方をとるのか、今までの仕事のやり方をとるのか決めて欲しい」と問われたため、「一緒に仕事ができないのなら辞めてくれませんか」と答え、話し合った結果、A社員が退職することを確認した。しかし、後日A社員から今回の退職は、自分から辞めたつもりはない。会社の都合に従って退職したのだ。これは解雇であるとして、解雇の手続きを求められた。さらに解雇予告手当を支払いの請求もされている。会社としてどう対応すればいいのか?
アドバイス
解雇とは、一般に、使用者が労働者に対し、日付を特定するなどして明確に労働契約の解約を一方的に通告することである。一方、使用者からの「辞めて下さい」「辞めて欲しい」などの発言は、使用者が労働者に退職を勧め、合意を促す退職勧奨である。退職勧奨は、あくまでも事実行為として退職を勧めるものであるため、応じるか否かは労働者の自由な判断である。
ご相談の場合は、退職の発端は解雇通告ではなく、使用者からの退職勧奨を労働者が承諾したものと考えられる。双方に合意があり退職は有効であると考えられる。であるから解雇の手続きをする必要もなければ解雇予告手当の支払う義務も会社はない。しかし、口頭での話合いでの合意だと、後になって今回のA社員のように退職の理由は解雇だと主張される可能性がある。話合いで退職の合意に至ったのであれば、その時書面で退職願等の書類を提出してもらうのもリスク防止のための一策であった。なお、労働者からなんら退職の意思が示されていない中で、使用者からの退職勧奨に基づき退職に至った場合には、いわゆる会社都合の退職として扱われる。
相談内容
社員10名ほどが働く企業を経営している。昨日、勤続4年目のA正社員が突然退職届を提出してきた。退職日は2週間後の日付である○月○日付である。そして最後の労働日の14日間を今まで使っていなかった有給休暇の権利を行使するという。今A正社員に辞められると業務の進行で困る。2週間後の日付で退職など認められないし、有給休暇消化などもってのほかである。なんとか退職の意思を撤回させることはできないか。
アドバイス
労働者には、職業選択の自由【憲法第22条】があり、本人の意思が固ければ、辞職そのものを撤回させることは難しい。また年次有給休暇は労働者の権利であり【労働基準法第39条】、請求された日に与えなければならない。使用者には業務の正常な運営に影響がある場合には時季変更権が認められる可能性があるが、今回の場合、退職日を超えて時季を変更することはできないので、労働者の請求した日に与えなければならない。今後企業ができる対策として、就業規則を整備し、辞職する場合は1か月前に申し出ること等定めておくなどが考えられる。ただし、退職をめぐって労働者と感情的にトラブルになった場合、労働者が「明日から出社しない!」と感情的に主張してきた場合、このような労働者に対して有効な手段とはいいがたい。せいぜい退職届を出してから2週間経たないと退職できない法律【民法627条】を紹介し、おだやかになだめ、話し合いを行うことになる。年次有給休暇については普段から消化できる社内環境にし、未消化日数を貯めさせないようにする。今回のケースでは、話し合いで解決できるのであれば、辞職の撤回を打診してみる。それが無理であるなら、退職日を後ろへずらし、ほかの社員へ業務の引きつぎのための出社の協力をお願いする等考えられる。
相談内容
当社は経営悪化により、経営が苦しく、役員の報酬カットや希望退職の募集など行い何とか会社を経営してきた。高年齢で比較的賃金の高い社員を解雇することにより人件費を圧縮したいが、何か問題は考えられるか。
アドバイス
経営悪化によりリストラを行う場合、いきなり労働者に対して解雇通知を行うのではなく、まず退職してほしい社員と話し合いを行い、場合によっては色の良い条件をつけ、退職を促すのが一般的である。ご相談内容だけでは具体的にわからないが、話合いをしたが退職勧奨に応じてもらえなかったパターンだろうか。会社の経営不振等を理由とする労働者の「整理解雇」については原則として以下の4要件をすべて満たす必要が判例上必要である。
- 経営上の必要性
- 解雇回避の努力
- 人選の合理性
- 労使間での協議
倒産寸前に追い込まれているなど、整理倒産をしなければならないほどの経営上の必要性が客観的に認められること。
配置転換、出向、希望退職の募集、賃金の引き下げ、その他整理解雇を回避するために、会社が最大限の努力を尽くしたこと。
勤続年数や年齢など解雇の対象者を選定する基準が合理的で、かつ、基準に沿った運用が行われていること。
整理解雇の必要性やその時期、方法、規模、人選の基準などについて、労働者側と十分に協議をし、納得を得るための努力を尽くしていること。
労働契約終了の4つのパターン
1、解雇
解雇とは、使用者が労働者に対し、一方的に労働契約を解除することであり、解雇される労働者の承諾や了解は必要ない。一般に、解雇は、社長や人事部長など責任ある立場の人から、日付を特定するなどして労働者に明確に書面で通告される。
解雇には、大きく3種類ある。
1.労働者の落ち度(非違行為=無断欠勤や遅刻などの職務懈怠、勤怠不良等)、能力や適性の欠如などを理由とする“普通解雇”
2.労働者が重大な企業秩序に反する行為を犯したことへの処分として行われる“懲戒解雇”
3.不況による業務の縮小、事業所の廃止、経営の合理化などにより人員整理を目的として行われる“整理解雇”
2、退職勧奨による合意に基づく労働契約の終了
退職勧奨とは、使用者が労働者に退職を勧めることをいう。退職勧奨は、あくまで使用者が労働者に退職を勧めるものであり、応じるかどうかは労働者の判断となる。対象者を拘束するなど民事上問題のある退職勧奨は、たとえ退職の合意を取りつけたとしても不当な退職勧奨として無効となる【民法第96条第1項】。また、損害賠償される可能性があります【民法第709条】。
3、辞職(労働者からの退職)
労働者自らの意思に基づく一方的な退職は辞職(自己都合退職)と呼ばれます。労働者には、職業選択の自由【憲法第22条】があり、辞職そのものを制限する法規定はない。法的には、期間の定めのない労働契約の場合、労働者が退職届を提出するなど辞職の意思表示をした後(使用者に労働契約の解約を申し入れた後)、2週間を経過することで当該契約が終了することが原則です【民法第627条第1項】。一方、有期労働契約期間途中の辞職については、傷病で労務不能な状態になったなどの「やむを得ない事由」が必要であるとされている【民法第628条】が、あらかじめ定められた契約期間が1年を超えて3年以内の場合でその契約が1年を経過した後は、原則として、労働者は使用者に申し出ることによりいつでも辞職することができる【労働基準法第137条】。また、使用者が合意した場合には、いずれの場合でもいつでも退職することができる。
労働者自らの意思に基づく退職が自己都合退職、使用者側の判断等による退職が会社都合退職とよばれる。一般に辞職は自己都合退職ですが、解雇は、使用者の判断により労働契約が一方的に解除されるものであるため、会社都合退職です。「辞めてくれ」などの使用者からの退職勧奨による退職も会社都合であることが基本です。
4、定年や労働契約期間満了に基づく労働契約の終了
就業規則で定める定年に達したとき、または有期労働契約で契約期間満了を迎えた時、その時をもって自動的に労働契約が終了する。
就業規則についての相談
相談内容
社員5名ほどが働く企業を経営している。知り合いから就業規則を定めておいたほうがいいと言われた。労働基準法では常時10名以上の社員がいるのであれば、就業規則の作成義務があるということは知っている。うちはずっと5名でやってきたし、今後も従業員はそれほど増えないだろう。下手に就業規則など作ると自分がそれに縛られるのではないか。それでも就業規則を作成したほうがいいのか。
アドバイス
就業規則を作成し、整備しておくことは企業経営に大変メリットがあります。
1.会社の仕組みをはっきりさせることができる
会社に社員が少なく、創業当初であれば明文化されたルールがなくても問題なく会社を経営できるかもしれません。ただし、今後社員の人数が増えると社員一人ひとりとのコミュニケーションが希薄になり、ふとしたことがきっかけである日突然労働問題が生じることがあります。そうなったとき、その対応に多大な時間を要することになります。つまり、社長個人の力だけではやがて限界がきます。社長が本来すべき仕事に集中するためにも、効率化できるところは効率化しておいたほうがよいです。例えば、問題が発生するごとに社長の裁可を仰いでいたのでは会社の発展は望めません。この問題を解決してくれるツールの一つが、就業規則です。つまり、社長の考えを文章にすることで、社員に知ってもらうことができる。また、社員に徹底することで会社の仕組みをはっきりとさせ、効率化を図ることもできるのです。
2・労使のトラブルを事前に予防できる
労使トラブルの原因の大部分は社内のコミュニケーション不全によるものが大半です。一筋縄にはいきませんが、就業規則を整備しておくことによって、かなりの労使のトラブルを予防できます。労使トラブルは年々増加の一途をたどっています。労使のトラブルを防止するための就業規則を作成して、社員によく説明をすることで、トラブルを未然に防止することができます。
就業規則を作成し、整備しておくことは企業経営に大変メリットがあります。デメリットは特に考えられませんが、あえてあげるなら最新の法令に適用させていくための手間でしょうか。そのようなことで就業規則の作成をためらうのはもったいないことです。ぜひ就業規則の作成・変更はアクト経営会計事務所にご相談ください。
使用者からの賃金の計算方法についての相談
相談内容
当社では、週3日勤務で午前10時から午後2時までを労働時間とする時間給のアルバイト社員がいる。先日、その社員から「先月支払われた賃金が自分の計算した金額と合わない」という問い合わせを受けた。労働時間はタイムカードで管理している。その社員は、しばしば必要な残務処理で実際の終業が午後2時を超えることがあるが、当社では30分単位で給料計算を行っているため、終業が午後2時30分を超えなければ追加の賃金は発生しないものとして処理している。今までこのやり方でずっとやってきた。このことを問題にしてきた社員もこの賃金の計算方法について問題はないか。
アドバイス
賃金は、労働者にその“全額”を支払わなければならない【労働基準法第24条】。そのため、例えば、賃金を30分単位で計算し、実際に労働していたにもかかわらず、30分未満の労働時間を切り捨てるなどの処理を行うことは、労働基準法の原則に反し適切な計算方法ではない。
一方、1か月における法定時間外労働の合計時間数に1時間未満の端数が生じた場合、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げるという処理は認められている【昭和63.3.14/基発150号】。
ただし、これは法定時間外労働に対する割増賃金に限られており、ご相談の場合は、法定労働時間(1日8時間・1週40時間)以内のものであるため、上記処理は適用されず、追加の賃金を支払う必要が生じる。
相談内容
当社の営業社員の雇用条件を基本給20万円、営業手当5万円(月20時間分の時間外手当を含む)と定めている。残業が多い月もあるが、通勤手当と毎月25万円を給与支給日に払っている。これで問題ないか。
アドバイス
事業場外のみなし労働時間制【労基法38条の2】よる取決めと錯誤しているケースやごっちゃに考えている中小経営者も多いが、適法に運用できているのであれば問題はない。話を元に戻すと、まずこの相談内容のような取決めは【固定残業代制度】と言われている。【固定残業代制度】が適法に運営されるには、まず残業代計算に当たっての基本部分を明確にし、【労基法37条】に基づく通常の計算方法で計算した額より有利な額を労働者に払わなければならない。また、雇用条件通知書や就業規則等で、固定残業代制度である旨と【労基法37条】に基づく通常の計算方法で計算した額が固定残業代より高額である場合は、差額を別途支払う旨の記載が必要である。ざっくりと営業手当5万円(月20時間分の時間外手当を含む)だけの記載では【固定残業代制度】とは扱われない。結局、固定残業代制度を導入するにしてもよく制度設計しないと、後で多額の未払い残業代を労働者に払わなければならなくなる危険性も考慮に入れたい。
使用者からの労基署の調査についての相談
相談内容
昨日、労働基準監督署から来署依頼書なる文面が届き、労基署へ行かなければならなくなった。あいにく指定された日時は用事があり、行くことができない。この調査にどう対応すればいいのか。
アドバイス
届いた文章がわからないので、具体的なことがわからないが、労基署から届く文章には、第○方面、担当監督官○○というように問い合わせ先が書いてあるので、まずは内容について問い合わせてみてはいかがだろうか。来署日時も理由があれば変更の対応を通常はしてもらえるようである。何もせず放置は絶対いけない。
労基署の調査
労基署には部署として労災課、方面(監督課)、安全衛生課などがある。労働基準法等の違反の調査をする部署は方面(監督課)である。方面(監督課)が行う調査は大きく4種類ある。
- 申告監督 労働者が監督署で申告手続きをとることにより、労基署が調査に動くもの
- 定期監督 違反が多そうな会社や業種にしぼって、労基署が調査にのりだすもの
- 集合監督 定期監督の一種ともいえるが、違反が多そうな会社や業種にしぼって来署してもらい、労基署が使用者にいろいろ話を聞くもの
- 災害時監督 労働災害が発生した場合、災害原因の究明と再発防止指導のために行われる調査。
労働災害の相談
相談内容
労働者死傷病報告は、労災事故が起きた時提出するものと聞いているが、いつ提出するのか、どんな場合でもすべて提出しなければならないのか。
アドバイス
仕事中、業務上での負傷・疾病により労働者が休業したとき、死亡したときは、事業主は所轄の労基署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。ただし、すべての場合に提出するものではありません。
- 労働者が4日以上休業したとき及び死亡したとき、労働者死傷病報告【様式23】を遅滞なく提出。
- 労働者の休業が4日未満(1~3日)のときには、4日未満の労災事故3か月分取りまとめえた労働者死傷病報告【様式24】を3か月ごとの期限までに提出。
労働時間についての相談
相談内容
所定労働時間が1日当たり7時間30分の会社を経営している。しかし、社員の退社時間は日によってバラバラであり、残業もよくしてもらっている。しかし、1日当たり8時間、1週間当たり40時間を超えて労働させてはならないと聞いたことがある。社員に適法に時間外労働として働いてもらうにはどうのようにすればよいか。
アドバイス
まず、【労基法32条】で休憩時間を除いて1週間に40時間、1日8時間を超えて労働させてはいけませんというのが定められている。時間外労働は、法定時間内残業と法定時間外残業に分けられる。この会社の例であれば、労働時間が7時間30分を超えて、8時間以内の部分が法定時間内残業で、8時間を超える部分が、法定時間外残業である。労働時間が8時間以内の30分の残業は、法定時間内の残業であるから特段手続きもなく、30分の賃金を別途払うのであれば、残業をさせても問題はない。(雇用条件通知書等で時間外労働有との記載有の場合)8時間を超える労働は32条違反となるので、原則は法定時間外労働をさせることはできない。しかし、【労基法36条】に基づく36協定を労基署に提出し、受付してもらうことにより、8時間を超える労働が32条違反でなくなり、適法となる。ただし、36協定を労基署に提出すると、すぐに従業員に対して残業命令をすることができるというわけでない。36条に基づく36協定の提出は32条違反になりませんよという効果が発生するのみである。【免罰的効果の発生】従業員に対して、業務命令として時間外労働を命じ、従事させるには、就業規則や雇用条件通知書に時間外労働がある旨と時間外労働に対する賃金計算方法が記載されていなければならない【労基法37条】。